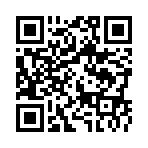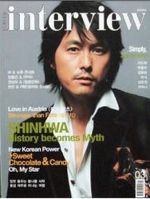2009年07月27日
劔岳 点の記〜ある映画バカの仕事〜

迷いに迷って、やっと観た「劔岳・点の記」。
前評判通りの本物の映画だった。
監督が今や日本を代表する名キャメラマン・木村大作、と聞いた時に、真っ先に頭をよぎったのが、「八甲田山」や「聖職の碑」「日本沈没」などの、森谷司郎監督と組んで撮った、かつての日本映画超大作だった。
それらは残念ながら、前宣伝ばかり先行して、作品の出来はイマイチなものばかりだった。
深作欣二監督と組んだ「復活の日」も明らかな失敗作。
つまり木村大作と聞くと、悪しき昭和の超失敗大作群を連想してしまうのだ。
ゆえに、この作品もそれらの焼き直しではないかという先入観から、なかなか観るのをためらっていたというわけだ。
しかし、木村大作は本気だった。
このCG全盛の時代にあえて一切CGを使わず、特殊効果に頼らずに、驚愕の映像を作り上げた。
それは本物だけが持つ圧倒的な迫力と息を呑む映像美。
陸軍測量部の柴崎芳太郎は、日本地図最後の空白地点を埋めるため、「陸軍の威信にかけて剣岳の初登頂と測量を果たせ」という命令を受ける。
柴崎は、案内人の宇治長次郎と剣岳の調査に入り、測量隊総勢7人で剣岳周辺に三角点を設置していき、ついに剣岳に臨む。
しかしガレキだらけの尾根、雪崩や暴風雨に続く困難に次ぐ困難が、測量隊の行く手を阻む。
命をさらしてまで、測量する意味はあるのかという迷いも7人の胸中によぎる。
一方、創立間もない日本山岳会も小島烏水らが最新の登山道具を揃え、剣岳山頂を目指していた。
今一度仲間としての結束を訴える柴崎。
果たして、柴崎たちは、無事剣岳山頂に立ち、地図作りの任務を果たすことができるのか。
そしてついに山頂に到達した一行が目にしたものは・・・
この映画が何よりスゴいのは、スタッフもキャストも全員が、実際に剣岳に自らの足で登っているという事だ。
ヘリコプターで山頂に機材や人を運ぶという事を一切せずに、ただひたすらに全員で登山して、実際の場所ですべて撮影しているのである。
なんと危険で労力のかかる、無謀とも言える撮影を敢行した事か。
しかし、監督木村大作がこだわりたかったのは、この一点なのだ。
ウソ偽りのない本物の映画を作りたい。
その一念のみで完成させたのがこの映画である。
その想いに応えたスタッフは勿論、浅野忠信、香川照之、松田龍平、仲村トオル等俳優陣がスゴいと思う。
彼らは無理してそんな過酷な撮影に臨まなければならないほど仕事に困ってはいない。むしろ引く手あまたな俳優たちだ。そんな彼らを突き動かしたものはなんなのか?
それが「映画愛」なのではないだろうか?
木村大作が文字通り命がけで挑んだのも、この「映画愛」あればこそ。
かつての映画人にとって、映画は命を賭けるに足る一大事だった。
黒澤組で撮影助手を務め一本立ちした木村大作にとって、映画とは命を削ってまで撮るものだったはずだ。
こんなに安易に誰でもが映画を撮れる時代になってしまったからこそ、「本物の映画作りとはこういうものだ!」というものを見せたかったのだろう。
演出面で興味深いのは、実際にモデルになった人物たちが通ったのと同じ道を俳優たちが登る事で追体験させ、その環境を与える事で、その役に成りきるというドキュメンタリー的な演出をしている点だ。
これはなかなか出来る事ではない。
役者は頭で役作りするのではなく、過酷な登山の経験を通して自分自身が登頂に成功した人物そのものになるのだ。
そしてこの映画が観る者にアピールするのは、効率一辺倒、拝金主義への痛烈な批判だ。
「大事なのは、何をしたかではなく、何のためにしたかである。」というセリフが出てくる。
これは見栄えのいい、マスコミが取り上げるような「何をしたか」の裏に、誰にも注目をされなくとも地道な努力を「何のためにしたか」を誇りに出来る人々がいることを教えてくれる。
測量のために前人未到の険しい山に登ったかつての無名の日本人たちの心意気や誇りを今こそ自分たち日本人は取り戻さなければならないのだ。
今自分がしている仕事は「何のために」しているのか、今一度じっくりと考えてみたいと思う。
今だ日本映画界にこんな本気の映画バカがいたことを日本人として映像制作者の端くれとして、誇りに思いたい。
この映画では類型的ながら「陸軍の横暴さ」や「マスコミの野次馬根性」も描かれている。
「陸軍」のお偉いさんは、何かと言うと「軍の威信に掛けて」ばかりだし、新聞記者は、日本山岳会とどっちが先に登頂するかばかりを煽り立てるし、いつの時代も変わらない。
そんな中で、初登頂を競い合う陸軍測量部と日本山岳会の、登頂後にお互い手旗信号で健闘を讃え合うシーンはジーンとくる。
スポーツマンシップにも似た爽やかな感動。
元々お互い勝ち負けへのこだわりなどなかった2チームが、周りに煽られていただけなので、素直にお互いを讃え合える。
このシーンは、偶然にも「真夏のオリオン」のラストシーンともダブる。
知力を尽くして戦った日本の潜水艦乗組員とアメリカ駆逐艦乗組員が、艦上でお互いに敬意を表し、健闘を讃え合うシーン。
これらに共通するのは、敵味方でありながら同じ目的のために命がけで事を成した男たちの共感、仲間意識なのだろう。
木村大作監督が特に強調したかったのが、まさにこの「仲間意識」。
今こそ日本人は、この「仲間意識」を持って、同じ目的に向かって一丸となるべし!というメッセージを感じる。
そしてこの思いがエンドロールで明快になる。
いつもの見慣れた、制作、脚本、撮影、撮影助手、監督、監督助手、などの序列を一切排した、ただ「仲間たち」の名の元に、全く同列で流れるスタッフ/キャストのエンドロール。
苦楽を共にした「仲間たち」への最大の「賞賛」がここに見て取れ、その想いに目頭がまた熱くなってしまうのだ。
Posted by Toshizo at 16:58│Comments(0)