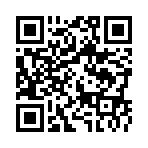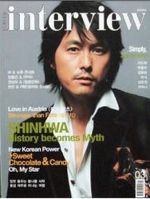2009年02月23日
日本映画のあるべき姿/祝おくりびと外国語映画賞受賞

やりましたね。
前評判は高く、日本国内でも賞を独占してましたけど、あんな日本人にしか理解できそうもない映画が、まさか外国語映画賞を獲るとは。
スタイル(様式)こそ違え、「死者を送る気持ち」は万国共通なんですね。
日本固有の価値観だと思われたものが、実は世界にも通用する普遍的なものだったということですね。
これは、日本映画のあるべき姿のお手本と言っていいでしょう。
ハリウッドに追従していても敵うわけがありませんから。
大袈裟に言えば、日本が、日本人が、国際社会の中でどう生きていくか?
何が出来るのか?
その答えもここら辺にあるのかも知れません。
やはり、私たち日本人がまず日本を知ることですね。
日本を知る為にも、是非この映画を劇場で観て下さい。
これから全国で再上映されるはずですから。
2009年02月18日
チェンジリング〜人間そのものを描くということ〜

クリントイーストウッド監督、期待の新作。
試写会で観て来た。
ある日突然、消えた息子。
5ヶ月後に帰って来た彼は別人だった。
この子は誰?私の子どもはどこへ?
1928年、ロサンゼルス。
魂で泣く本当にあった物語。
どれだけ祈れば、あの子は帰ってくるの?
このチラシの宣伝文句を読んで、どんな映画を想像するだろう?
お涙頂戴の母子の愛情物語?
を想像すると、違う。では
魂が入れ替わるホラーサスペンス?
人格転移のサイコサスペンス?
社会派の陰謀ミステリー?
う〜ん、そのどれでもない。
イーストウッド監督が、そんな一筋縄でいく映画を撮るはずが無い。
これは「とんでもない」映画だ!
母子の感動物語であり、警察の不正・腐敗告発映画でもあり、実録連続殺人鬼モノでもあり、どんでん返しミステリーでもある。
これらの要素がすべて詰まった、もの凄く「とんでもない」映画だ。
ズッシリと重く観る者にのしかかってくる映画だ。
2時間20分、息をつく間もなく、たっぷりと「人間ドラマ」を見せてくれる。いや「人間そのもの」を見せられたというべきか。
「人間」の「愛情の深さ」「猾さ」「醜さ」「怖さ」「罪」「信念の力」「正義」ありとあらゆるモノをこれでもかこれでもかと、胸をえぐるように見せつけられる。
前述の宣伝文句に騙されてはいけない。あんなモノはこの映画のほんのさわりの部分しか表現出来ていない。
観ていない人には全く何のことかわからないだろうから、ストーリーに少し触れてみよう。
1928年ロサンゼルス。クリスティン・コリンズ(アンジェリーナジョリー)は、9歳の息子、ウォルターと二人で平和に暮らしていた。
しかしある日突然、息子が忽然と姿を消す。
警察に捜査を依頼するも、全く本気で捜索してくれない。
そして5ヶ月が経って、警察から知らせが入り、息子が帰って来る。
しかし、息子を名乗る少年は全くの別人だった。
それは手柄を挙げたい警察の「でっち上げ」だったのだ。
警察は、我が子ではないと主張する母の言葉を黙殺するばかりか、強制的に精神病院に入れ、我が子と認めるまで退院させないという卑劣な手段を取る。
そんなある日、不法入国していたひとりの少年が逮捕される。
そしてその少年の口から、前代未聞のアメリカ犯罪史上最悪の連続少年誘拐殺人事件が語られることになる。
警察はウォルター少年も含む消息不明の少年の写真を彼に見せる。
誘拐された人数は20人以上。数人は逃げ延びているらしい。
果たしてウォルター少年の消息は?
やがて犯人が捕まり、事件の全貌が明らかになるかに思われたが。。。
過酷な運命は、まだ始まったばかりだった。
アンジェリーナジョリーが、まさに主演女優賞モノの熱演を見せる。
本当に涙が枯れ果ててしまったのではないかと思えるほどの、やつれ果て振りがスゴい。
それでも尚、息子の生存を信じ続け、警察の不正とも戦い続ける。
こんな役は10年に1度、彼女にとっては演技開眼のまたとないチャンスだったろう。
クリントイーストウッドの「人間」を見る目の鋭さ、深さも感動モノだ。
「ミリオンダラーベイビー」以降、1作毎に凄みを増していくようだ。
そいてついにここまで来た。
これほどまでに「人間」が描かれた映画は、ちょっとないだろう。
すでに本年度ナンバー1に間違いない。
これは是非、劇場でじっくりと、腹をくくって観て欲しい映画だ。
恐らく大多数の人の想像を遥かに超えた、とんでもない映画だ。
大分の映画情報まるわかり「MOVIE-S!」
2009年02月15日
12人の怒れる男〜ロシアの今を浮き彫りにする〜

1957年公開のシドニールメット監督の出世作、アメリカ映画史上に燦然と輝く法廷ドラマの古典的名作がロシア映画としてリメイクされた。
冷戦時代、アメリカ映画をロシアでリメイクなどということはありえないことだったはずだ。
それが今、何故リメイクされたのか?
ロシアでのリメイクにどんな意味があるのか?
そんな疑問の答えを期待して観てみた。
もちろん、12人の陪審員が、1人の少年が起こした殺人事件を裁くという設定はオリジナルのまま。
違うのは舞台が現在のロシアで、被告の少年がチェチェン人ということ。
チェチェン人の少年が養父であるロシア人を殺した事件。
有罪は確定的と思われ、12人全員が「有罪」で簡単に審議終了の予定だった。が。。。一人の男が「無罪」を主張し、あらためて審議し直すことになる。
その過程で、12人一人一人の「人生」が浮き彫りにされ、事件の詳細が見えてくるにつれ、次第に「無罪」に傾いていく者が増えていき。。。
ついに全員が「無罪」で確定するかに見えたが。。。
そこには、オリジナルとは異なる「切なく衝撃的なラスト」が待ち受けていた。
少年の背負わされた「現実」の前に、男たちはどのような結論を導き出すのだろうか?
ロシアの「恥部」といわれ、これまでほとんど報道されてこなかった「チェチェン紛争」の「真実」。
その「恥部」にメスを入れることこそが、このリメイクの意図するものだったのだ。
オリジナルの設定のみをいただいて、全く別の時代に、全く別の世界で、「ロシアの今」を鋭く描きながら、オリジナルに勝るとも劣らない傑作が生み出された。
リメイクとはこうありたいものだ。
これはアカデミー外国語映画賞にノミネートされるのも頷ける傑作だと思う。
三谷幸喜のパロディ「12人の優しい日本人」も、もし日本に陪審員制度があったらという設定の傑作だったが、今もし日本映画でこれを本気でリメイクするとしたらどんな映画になるだろうか?
今の日本が抱える問題とは?日本の現実が浮き彫りにされる傑作になりえるだろうか?
周防正行監督辺りに本気で取り組んでもらいたいものだ。
2009年02月09日
20世紀少年 第2章/最後の希望〜中継ぎの宿命〜

20世紀少年、待望の第2章。
壮大な物語の真ん中部分にあたる、2015年の世界。
謎の教団「ともだち」は、世界制覇を遂げていた。
だが、本当の恐怖はまだこれからだった。
「しんよげんのしょ」の存在が明らかになったのだ。
「2015年、新宿の教会で、救世主は何ものかに暗殺される」
救世主とは誰なのか?
「ともだち」の正体は?
叔父・ケンジの遺志を継ぐ「遠藤カンナ」は、ケンジの幼馴染みの力を借り、悪の組織「ともだち」に敢然と立ち向かっていく。
そして「運命の日」。暗殺されるのは誰か?
カンナたちは世界を救うことが出来るのか?
原作を読んでいない人は、多分どんな話か分からないだろう。
さらに第1章を観ずに第2章を観たら尚更意味不明だろう。
そうでなくても複雑に絡み合ったストーリー展開なので、きっちり「予習」をしてから観た方がいいと思う。
第2章の主人公は「カンナ」。
誰が演じるか?もっとも注目を集めたキャスティングだろう。
結果、この「平愛梨」、カンナに生き写しだった。
「目ヂカラ」がある。物語を牽引していけるだけの魅力があると思う。
芸能界引退を考えていたグラビアアイドルが、起死回生で掴んだビッグな役だった。まさに彼女に取って「最後の希望」がこの映画だったわけだ。
映画の出来は、相変わらずノンストップであっという間に2時間半突っ走る「ロックンロール」な映画になっている。
ただ三部作という構成上、野球で言えば「先発」「中継ぎ」「押さえ」の「中継ぎ」のような中途半端な印象は拭えない。
あまり山場を作らず、0点に抑えて当たり前の「中継ぎ」。
「先発」「押さえ」の投手に比べて、どうしても印象が薄い「宿命」なのだ。
かといって「中継ぎ」がいなければゲームは成立しない。
単独で評価しづらいのが今作だが、3部作通しで観た時、橋渡しとしての役目は立派に果たしたと言える作品だろう。
いつになく、こんな意味不明な評価になって申し訳ないが、原作ファンなら充分に満足出来る出来だとは思う。
くれぐれも原作も読まず、第1章も観ずに、これを観て、「訳わかんない」の評価を下さないようお気をつけ下さい。
2009年02月06日
その土曜日、7時58分〜銃容認社会の怖さ〜

名匠シドニールメット監督84歳の新作「その土曜日、7時58分」
舞台はニューヨーク、一見誰もがうらやむ優雅な暮らしをしていた会計士アンディは、離婚し娘の養育費も払えない弟ハンクに、禁断の企てを持ちかける。
それは実の両親が営む宝石店への強盗計画だった。
強奪した宝石は保険に入っている為、誰も困らない完璧な計画のはずだった。
そしてその決行の日、土曜日、7時58分。
3発の銃弾が店に鳴り響いた。
たったひとつの誤算を引き金に、事態は最悪の結末へと転がり堕ちていく。
次々にあらわになっていく「家族」の真実。
急速に追いつめられて行く二人の運命は。。。
ミステリー風味の人間ドラマ。
なのでくわしくは書けませんが、強盗計画の破綻をきっかけに、家族の秘密が次々と暴かれて行く様は、超一級のミステリーと言っても過言ではありません。
84歳にしてこの完成度、さすが並の監督ではありませんでした。
それにしても、いつも思うのは「たった1発の銃弾が運命を変えてしまう」銃容認社会の怖さ。
最近のアメリカがおかしくなっているのは、さすがにもう誰の目にも明らかだと思いますが、やはり絶対にNOと言わなければいけないのは、「銃容認社会アメリカ」の「護身の為なら銃を持ってもいい」という「習慣」です。
アメリカにシンパシーを感じ、アメリカのファッションやカルチャーに影響を受けるのもいいですが、この間違った「習慣」だけは、絶対に真似して欲しくない。日本に入って来て欲しくない「習慣」です。
これだけ無差別殺人など凶悪犯罪が増えて来ると、日本もそうは言ってられなくなるのかもしれません。
ただ、日本にはまだ「銃」が少ないので、このくらいで済んでいるという見方も出来ますね。
2009年02月04日
007/慰めの報酬〜新生ボンドが無くしたモノ〜

新生ボンド、ダニエル・クレイグの2作目。
前作「カジノロワイヤル」の続編。
前作からボンド役が変わるにあたって、それまでと大きく変わった点が、リアリズムの追求だった。
脚本を社会派ドラマに定評のあるポールハギスを起用したのが、大きな変更点だと思うが、狙い通り、悩み苦しむ泥臭い生身のボンドを生み出すことに成功したと言えるだろう。
そして今回の2作目も、そのままのボンドが登場する。
敏捷で高い身体能力を持ち、冷静沈着、冷酷非情な新生ボンドは、ダニエル・クレイグのキャラとも合って、新たなファンを獲得しただろう。
確かにこんなボンドもありだろう。
でも、なにかちょっと違う。
この違和感はなんだろうと考えてみる。
それは、自分がジェームズボンドに抱いて来た「英国紳士」のイメージとの「ズレ」なのだ。
特に初代のコネリー・ボンドには「それ」があった。
「それ」とは、一言で言えば「洒落っ気」だろうか?
例えばこんなシーン。
ボンドが留守の間に敵の情婦が忍び込み、バスタブに浸かっている。
それを見つけるボンド。
女がバスタブから出ようと「何か身に付けるものを取ってくださる?」と頼むと、ボンドは彼女が脱いでいた「サンダル」を拾い上げて渡そうとする。
またはこんなシーン。
部屋に忍び込んでいた敵に襲われ格闘になり、ボンド危機一髪。
機転を利かせて、部屋にあった「花瓶」で敵を殴り倒す。
その後何事も無かったようにネクタイを直し、割れた花瓶をデスクに置いて、ついでに花も差し直す。
といったシーンに見られる「洒落っ気」や「茶目っ気」
「センスオブユーモア」
それこそ、自分が憧れの「英国紳士」に抱く粋なイメージだった。
その部分がクレイグ・ボンドでは影を潜めてしまった。
そんな「洒落っ気」はリアリティがないと判断されたのだろうか?
冷静沈着、感情を抑えて、無口で、人前では笑顔も見せないボンド。
言ってみれば「ボンドがドイツ人になってしまった」ような感じだ。
まぁこの2作は、ボンドが一流の諜報部員になるまでの成長過程なので、そんな「余裕」はないとも取れる。
次回3作目で、そんな「余裕」が出て、真の英国紳士な諜報部員になれているかどうか、見物だ。
2009年02月03日
BOBBY〜アメリカの光と影〜

「BOBBY 」とは、ロバートFケネディの愛称。
1968年、ロサンゼルスのアンバサダー・ホテルで暗殺された、ロバート・F・ケネディ上院議員。次期大統領として国民の希望の星だったボビィ。この映画は、暗殺当日、ホテルに居合わせた22名の人間模様を描いた作品である。
退職した老ドアマン、不倫している支配人とその美容師の妻、ベトナム行きから逃れるために結婚式を挙げるカップル、ドジャースの歴史的試合のチケットを手に入れたメキシコ人ウェイター、LSDでトリップするボランティアスタッフの若者たち、アル中の落ちぶれた歌手、22人の様々な人生が交錯し、それぞれの喜びや苦悩が浮かび上る。それらの登場人物を、アンソニーホプキンス、ハリーベラフォンテ、シャロンストーン、デミムーア、マーティンシーン、ヘレンハント、イライジャウッドといった超豪華な顔ぶれが演じる。
いわゆる「グランドホテル形式」の作品だが、実話が元になっているだけに、クライマックスの「その瞬間」に向かって緊張感のある展開を見せる。
彼らの思いがアメリカの希望の星、ロバートケネディの登場によって最高潮に達した時、あってはならない悲劇が起きる。
当時の映像も交えた衝撃のクライマックスにより、この作品を単なる市井の人々の人間ドラマで終わらせないメッセージ性の強い作品にまで昇華させている。
最も心に強く残るのは、クライマックスの銃撃後の混乱の映像に被せられるロバート本人の当時の肉声スピーチだ。死の二ヶ月前の「暴力終結」を提唱したスピーチ。その全文を書き出してみた。
アメリカでの心ない暴力について。
暴力は国の名誉を汚し、人々の命を奪います。
それは人種に関係ありません。
暴力の犠牲者は黒人、白人、富者、貧者、若者、老人、有名、無名。
何よりもまず彼らは人間だと言うこと。
誰かに愛され必要とされた人間なのです。
誰であろうと、どこで暮らそうと、どんな職業であろうと、犠牲者になり得ます。無分別な残虐行為に苦しむのです。
それなのに今も尚、暴力は私たちのこの国で続いています。なぜでしょう?
暴力は何を成し遂げたでしょう?何を創り出したでしょう?
アメリカ人の命が別のアメリカ人により不必要に奪われる。
それが法の名の下であろうと、法に背くものであろうと、
一人または集団によって、冷酷に計算して、または激情に駆られて、
暴力的攻撃によって、または応酬によって、
一人の人間が苦労して自分や子どものために織り上げた生活や人生が暴力で引き裂かれる。
暴力はすなわち国家の品位を貶めることです。
それなのに私たちは暴力の増長を容認する。
暴力は私たちの人間性や文明社会を無視しているのに、私たちは力を誇る者や力を行使する者を安易に賛美する。
自分の人生を築くためなら他者の夢さえ打ち砕く者を私たちはあまりにも安易に許してしまう。
でもこれだけは確かです。
暴力は暴力を生み、抑圧は報復を生みます。
社会全体を浄化することによってしか、私たちの心から病巣を取り除けません。
あなたが誰かに人を憎み恐れろと教えたり、その肌の色や信仰や考え方や行動によって劣っていると教えたり、あなたと異なる者があなたの自由を侵害し、仕事を奪い、家族を脅かすと教えれば、あなたもまた他者に対して同胞ではなく敵として映るのです。
協調ではなく力によって征服し、従属させ支配すべき相手として、やがて私たちは同胞をよそ者としてみるようになる。
同じ街にいながら共同体を分かち合わぬ者。
同じ場所に暮らしながら同じ目標を持たぬ者として、共通するものは恐れとお互いから遠ざかりたいという願望。
考え方の違いを武力で解決しようという衝動だけ。
地上での私たちの人生はあまりに短く、なすべき仕事はあまりに多いのです。
これ以上暴力を私たちの国ではびこらせないために。
暴力は政策や決議では追放出来ません。
私たちが一瞬でも思い出すことが大切なのです。
共に暮らす人々は皆同胞であることを。
彼らも私たちと同じように短い人生を生き、与えられた命を最期まで生き抜きたいと願っているのです。
目的を持ち、幸せに満ち足りた達成感のある人生を送ろうと。
共通の運命を生きる絆は必ずや、共通の目的を持つ絆は必ずや、私たちに何かを教えてくれるはずです。必ずや私たちは学ぶでしょう。
周りの人々を仲間として見るようになるはずです。
そして努力し始めるでしょう。
お互いの敵意をなくし。お互いの心の中で再び同胞となるために。
このスピーチの二ヶ月後に本人が心ない暴力の前に希望に満ちた人生を断ち切られてしまうとは。。。
歴史に「if」はない。と言うが、もしJFKが、弟のロバートが凶弾に倒れていなかったら、アメリカという国は変わっていただろうか?
映画の中のスピーチのシーンで、「思いやりのある国」を目指すと言っていたのがとても印象に残った。
今、この映画が作られ、このスピーチが引用された「意味」を考えなければいけないと思う。
2009年02月02日
ザ・フォール/落下の王国〜映画とCMの違い〜

CMディレクター出身のターセムという監督が構想26年、撮影に4年を費やしたという作品だ。
1915年、映画のスタントマンをする主人公ロイは、落馬事故で両足を骨折し入院する。その病院で、同じく木から落ちて左腕を骨折した少女・アレクサンドリアと出会う。
職を失い、恋人も奪われたロイは自暴自棄になり自殺を考える。
そしてベッドに寝たきりの彼は、少女を手なずけ、自殺の為の薬を取って来させようと企て、彼女に架空の物語を話して聞かせ、次第に親しくなっていく。その物語は、5人の勇者が権力者に復讐する為の旅に出る、壮大なファンタジーだった。
物語に引き込まれるアレクサンドリア。
次々と倒されていく勇者達。
物語の主人公にも現実のロイと同じ最後の時が迫ろうとしていた。
その時、主人公に感情移入したアレクサンドリアは。。。
兎に角、宣伝文句通り、「色彩の鮮やかさ、映像美の美しさ」に息をのむ。
世界24カ国以上、13カ所の世界遺産でロケーションしたと言う映像の美しさは圧巻だ。
それに加えて、日本人デザイナー、石岡瑛子の衣装デザインが素晴らしい。
役者より衣装が主役といってもいいほどの素晴らしさだ。
CMディレクターらしい1カット1カット、グラフィカルなアートを観るようなこだわりの映像。
偶然だが「パコと魔法の絵本」にちょっと設定が似ている。
しかも監督はどちらもCMディレクター出身。
自分はずっとCM業界で、そのたった15秒にこだわった丹念な映像作りの現場を体験して来ながら、この密度で映画を作ったらどんなスゴい映画が出来るだろうと思って来た。
その思いを現実にした監督の筆頭が、リドリースコット監督だった。
そして、この作品のターセム監督や、日本の中島哲也監督も、それを実現した監督だろう。
が、しかし、映画とCMには決定的な違いがある。
「長編小説」と「俳句」ほどの違いだろう。
撮影の手順、編集、音楽など基本的な作業は同じだが、最も大きな違いは「脚本」の存在だ。
どんなに素晴らしい映像を見せられようとも、脚本がつまらなければ、それはつまらない映画になってしまう。
そうやって失敗した異業種監督もまた少なくない。
この作品も映像美は絶賛に値するが、導入以後のストリー展開の単調さが欠点と言わざるを得ない。導入部とエンディングは悪くないだけに、途中にもう少し二転三転する起伏を付けて欲しかったと思う。
その点が残念な作品だった。